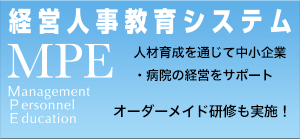みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年6月27日金曜日です。
#人材確保等支援助成金 #キャリアアップ助成金 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #賃金制度設計 #セッション付きオーダーメイド研修
https://www.mpejinji-club.jp/496
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/545
硬式の高校野球の加盟校と部員数が11年連続で減少しており、2025年度は昨年より1,650人少ない12万5,381人となっています、社会全体の変化や教育現場の課題が複合的に影響しているとも言われています。
少子化の影響
– 子どもの数自体が減っており、どの部活動も人材確保が難しくなっています。
– 特に地方では部員数が1桁の学校も増えており、チーム編成すら困難なケースも。
スポーツの多様化
– サッカーやバスケ、eスポーツなど、選択肢が広がったことで野球一強の時代ではなくなりました。
– 野球はルールが複雑で試合時間も長く、若年層にとってはハードルが高いと感じられることも。
部活動のスタイル変化
– 丸刈りや厳しい上下関係など、伝統的な文化が敬遠される傾向にあります。
– 実際に「丸刈り」を採用している学校は5年前の76.8%から26.4%に激減。
学校の運営事情
– 教員の働き方改革により、顧問の負担が問題視され、野球部の維持が難しくなっている学校もあります。
野球ファンの1人としては野球の魅力を伝えていくのもひとつだなと・・・・
さて
企業が持続的に成長していくためには、人材の確保が欠かせません。
しかし、日本の人口減少は避けがたい現実であり、従来のように潤沢な労働力を確保することは困難になっています。
このような環境下においても企業の持続的な成長を促進するためには、雇用形態や労働時間の制約を超えて、多様な人材が活躍できる環境づくりが求められます。
そのためには、多様なバックグラウンドをもつ従業員同士が協力し合い、業務に取り組む職場環境を整えることが重要です。
年齢、文化・社会環境、価値観、職務経験などが異なる個々の社員を理解し、それぞれの強みを活かしながら成果に結びつけていく必要があります。
その基盤となるのが、相互理解を深めるための意思・意図・感情・情報の共有、つまり「コミュニケーション」です。
特に、上司と部下の間における適切な対話と指導は、信頼関係の構築に直結します。
一人ひとりに合わせた柔軟な対応によって、信頼関係が築かれれば、部下は上司の言葉に耳を傾け、より良い仕事につなげようとする姿勢が生まれます。
同時に、上司も対話を通じて部下を深く理解し、それぞれに合った指導方法を見出せるようになります。
信頼関係を築くためには、まず「傾聴の姿勢」を持つことが基本です。
その上で、部下の主体性を引き出す「コーチング」と、業務の手順や知識を教える「ティーチング」の両輪を、状況や成長度に応じて使い分けることが求められます。
コーチングにより部下の思考力や行動力を引き出し、ティーチングで必要な知識や技術を伝えることで、部下は自ら考えながら業務に取り組む力を身につけていきます。
このサイクルを繰り返すことで、部下は主体性を持った働き方を習慣化し、組織全体の成長にも貢献できるようになるのです。