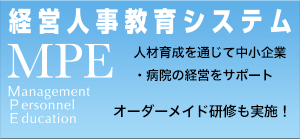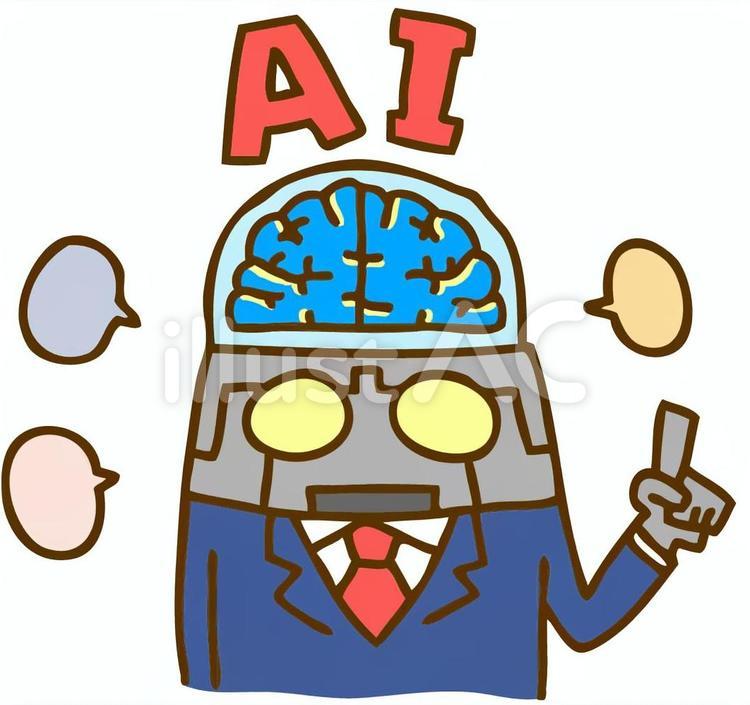
みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年7月3日木曜日です。
#人材確保等支援助成金 #キャリアアップ助成金 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #賃金制度設計 #セッション付きオーダーメイド研修
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
「心の健康」という見えない単位・・・・大学生に何が起きているのか?
かつて「大学生活」といえば、自由と可能性に満ちた時間として語られることが多かった。しかし、近年その舞台の裏側では、深刻な心の疲弊が静かに広がっている。相談窓口やカウンセリングルームを訪れる学生の数は右肩上がり。友達づきあい、学業、キャリアへの不安…そのどれもが「自己責任」として内面に押し込まれ、やがて心を蝕んでいく。
背景には何があるのだろうか。SNSによる過剰な自己比較、効率や成果が重視される教育環境、そして「失敗=終わり」とする社会のまなざし。これらは、若者の心に「見えない単位」の重圧を与えている。テストで測れない疲れ、通知表に現れない孤独——それらが積もり重なっているのだ。
特に注目したいのは、「人とつながること」への価値観の変容だ。かつては雑談や無目的な集まりが癒しの場であったが、いまや人と接するにも「意味」や「目的」が求められる。結果として、誰にも弱音を吐けないまま、ふとした瞬間に心が折れてしまう若者が増えているという・・・・・
では、どう向き合えばいいのか?
まず必要なのは、「助けを求めることは弱さではなく、スキルである」という認識の転換だ。そして大学や社会がその「助ける場」を日常の中に織り込んでいく必要がある。心の健康は、体の健康と同じように、誰にとっても当たり前に語れるテーマであるべきだ。
さて話は変わって、
伝わる言語化とは何か?
仕事を教えたり任せたりする際の基本手順は、次の通りです。
5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を用いて、具体的かつ細かく説明する
不安な点や不明な点がないか、相手と確認し合う
相手に、自分が行うべきことを復唱してもらう
伝わる言語化ができていない例
たとえば、「今日、クライアントに電話で新商品の購入を粘り強く提案する」という指示。
この一文からでは、
何をどのように話すべきか
どの程度“粘り強く”なのか
商品のどのポイントを訴求するのか などが伝わりません。つまり、これは“教えた”とは言えず、単なる表面的な指示に留まってしまいます。
リーダーに求められる「言語化力」=「明確化力」
リーダーにとっての言語化とは、「自分の考えや意図を、誰が聞いても再現できるレベルで明確に伝える力」です。
ただし、どれほど明確にしても、“相手に伝わらなければ意味がない”。
「伝わる」とはどういうことか?
わかりやすさとは、単なる情報の整理ではありません。
それはすなわち、 「把握できて、納得できて、再現できる」こと。 この3つが揃って初めて、“伝わった”と言えるのです。