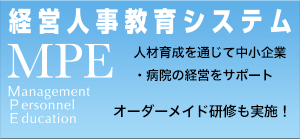みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年7月7日月曜日です。
#人材確保等支援助成金 #キャリアアップ助成金 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #賃金制度設計 #セッション付きオーダーメイド研修
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
今日は七夕です。
七夕(たなばた)のルーツは、中国から伝わった七夕伝説にあります。いくつかのバージョンが存在しますが、一般的な物語では、織姫と彦星が年に一度だけ再会を許されるというロマンチックな逢瀬が描かれています。そのため、七夕は恋愛がテーマの行事だと思われがちです。
しかし、ふたりが引き裂かれ、再会に至るまでの経緯に目を向けると、この物語には「技芸に励み、真面目に働くことの大切さ」を説く側面があることがわかります。
話は変わって、
「伝わらなかった」は、誰の責任か
何かを説明したとき、相手の反応が自分の想定と違っていた──そんな経験はありませんか?
「そんなつもりじゃなかった」「そんな意図はなかった」と思っていても、相手にそう伝わってしまったのであれば、その“伝わった内容”こそが結果であると受け止めなければなりません。なぜなら、コミュニケーションの結果は、常に受け手の解釈によって決まるからです。
あるいは、どれだけ一生懸命に説明しても、「よくわからなかった」と言われてしまうこともあるでしょう。そんなとき、つい「相手の理解力が足りない」と考えてしまっていないでしょうか?
もちろん、相手がその話を理解するための前提知識を持っていなかった、という可能性もあります。しかし、それを踏まえたうえで、「その前提を持っていないかもしれない相手に、どうすれば伝わるか」を考え、説明の仕方を工夫することが、伝える側の責任ではないでしょうか。
なぜなら、変えることができるのは、相手ではなく、自分の伝え方だからです。
「正解がない」ことへの向き合い方
コミュニケーションの結果が受け手によって決まるということは、同じ内容を伝えても、相手によって受け止め方が変わるということです。つまり、「これが正解」という唯一の答えが存在しない、ということでもあります。
この「正解がない」という状況に、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか。
ひとつの選択肢は、「どうせ正解がないのだから、あれこれ考えるのはやめよう」と諦めること。
もうひとつは、「正解がないからこそ、相手に伝わるように一生懸命考えよう」と試行錯誤を重ねること。
どちらの姿勢が、次のコミュニケーションに活かされるかは明白です。努力を怠った者と、工夫を重ねた者の差は、やがて大きな違いとなって現れます。
「受け手絶対主義」で臨むということ
だからこそ、これからは「受け手絶対主義」の姿勢でコミュニケーションに臨むことが大切です。
そして、正解がないからこそ、毎回の対話に真剣に向き合い、考え抜くこと。
「伝わるかどうか」は運ではなく、姿勢と工夫の積み重ねです。
そう信じて行動することが、コミュニケーションを上達させる唯一の道なのではないでしょうか。