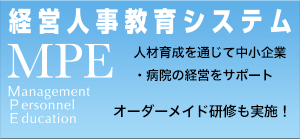みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年8月25日月曜日です。
#人材確保等支援助成金 #キャリアアップ助成金 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #賃金制度設計 #セッション付きオーダーメイド研修
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
危険な暑さが続く今年の夏、京都市東山区の建仁寺では、参拝者に少しでも涼を感じてもらおうと、本坊内に氷柱を設置する取り組みを今年から始めた。四方を回廊に囲まれた「潮音庭」に面して置かれた高さ約45センチの氷柱には、庭の緑が映り込み、見た目にも涼やかな雰囲気が漂う。建仁寺は「昔ながらの涼の取り方を知っていただき、景色とともに涼を感じていただければ」と話している。
さて話は変わって、
中小企業経営者が人事評価を重視しない理由を考えてみました。
- 経営資源の不足
制度設計や運用に時間・人材・コストがかかる。
「売上や現場対応が優先」という意識が強く、評価制度は“後回し”になりがち。
- 属人的なマネジメント文化
「顔を見れば分かる」「阿吽の呼吸でやってきた」という経験則が根強い。
経営者自身が現場をよく知っているため、制度よりも“肌感覚”を信じる傾向。
- 評価=対立の火種という誤解
評価を明示すると「不満が出る」「揉める」と考え、あえて曖昧にしている。
特に家族経営や長年の社員が多い企業では、関係性の維持が優先される。
- 制度への不信感・過去の失敗
過去に導入したがうまく機能しなかった、というトラウマ。
「評価しても昇給できない」「公平に運用できない」というジレンマ。
- “見える化”への抵抗と恐れ
評価制度は、経営者自身のマネジメント力や組織の課題を“見える化”する。
その結果、自分自身が評価されるような感覚になり、無意識に避けてしまう。
それでも、評価制度がもたらすもの
われわれが取り組んでいるような「心理的安全性」や「育成型評価」は、単なる査定ではなく、信頼と成長の土壌づくりなのです。
たとえば:
若手社員が「自分の成長が見える」と感じることで、定着率が上がる。また、上司と部下の対話が増え、感謝や承認の文化が根づくなど・・・・いろいろ変化が.
何よりも経営者自身が「人を育てる喜び」を再発見できることです。
人事の再起動(リスタート)を考えてみましょう・・・・