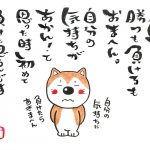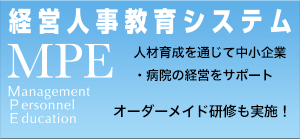みなさんこんにちは。今日は、令和7年10月7日火曜日です。
『明るく挨し、心に芯を、運は信じて、縁を結び、目指すは遥か、大きな夢』 をモットーにしている
下ちゃんです。
#人材確保等支援助成金 #Goodモチベーション診断 #人事制度設計 #組織診断
#リカレント教育 #賃金制度設計 #採用・定着・戦力化支援プログラム
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
制御性T細胞と聞いても、素人には何が何だかわかりませんが、ノーベル賞を受賞したという事実が、いかに偉大な業績であるかは伝わってきます。
スウェーデンのカロリンスカ研究所は、今年のノーベル生理学・医学賞を、大阪大学の坂口志文特任教授らに授与すると発表しました。受賞理由は「免疫が制御される仕組みの発見」です。
坂口教授らは、病原体を攻撃する免疫細胞の中に、免疫反応の暴走を抑える“ブレーキ役”として働く「制御性T細胞」を発見しました。この細胞の働きが弱まると、免疫細胞が体内の正常な組織を攻撃し、自己免疫疾患などの病気を引き起こすことも明らかにしました。
日本人の受賞という点も、何より誇らしく、心から嬉しく感じます。
さて話は変わって、
社員のメタ認知能力を高めるための方法について考える
社員自身がメタ認知能力を高めるためには、「モニタリング」と「コントロール」のトレーニングが重要です。 自分の行動や思考を客観的に確認する作業を「セルフモニタリング」と呼びます。長所や強みには向き合いやすい一方で、欠点や短所には正面から向き合うことが難しい場合もあります。 そのため、社員がメタ認知能力を高めるには、まず自分の弱点に対して逃げずに、意識的に向き合うことが第一歩となります。
セルフモニタリングを支援する手段として、ビジネススタイル診断や性格診断などのツールを活用することも有効です。これらを用いることで、社員は自身の強み・弱みを客観的に認識し、それらとどう向き合い、どう活かしていくかを考える機会を得ることができます。
セルフモニタリングによって改善すべき点が明確になったら、次はそれらを克服するための「セルフコントロール」を実践します。 なぜそのように感じるのか、なぜそのような行動をとるのかといった要因を分析し、対策を講じることがセルフコントロールにあたります。
たとえば、「特定の状況下で仕事への集中が途切れることがある」という課題を認識した場合、その要因が「リモートワーク中にWeb会議を連続して行った後の事務作業」であると分析できるかもしれません。 このような場合には、「作業場所を変えてみる」「スケジュールを集中力の高い時間帯に調整する」など、自分でコントロール可能な範囲で対策を講じることが考えられます。
社員一人ひとりがメタ認知能力を高めることは、個々の強みを活かすことにつながり、結果として組織全体のパフォーマンス向上も期待できます。 まずは、メタ認知能力の高い人の特徴を参考にしながら、社員自身にセルフモニタリングに取り組んでもらいましょう。診断ツールの活用も一つの有効な方法です。
また、社員が日常的にセルフモニタリングやセルフコントロールに取り組めるよう、人事部門としてもその機会を提供するなど、具体的な支援策を検討していくことが重要です。