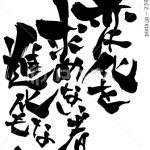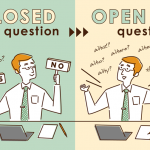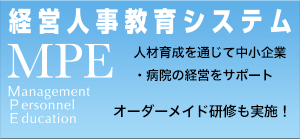みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年7月2日水曜日です。
#人材確保等支援助成金 #キャリアアップ助成金 #人事制度設計 #組織診断 #リカレント教育 #賃金制度設計 #セッション付きオーダーメイド研修
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
6月はやっぱり暑かった――「記録的な夏」のはじまりに思うこと
🔹「暑さ」はもう“異常”ではない
2025年6月、日本列島はかつてない暑さに包まれた。気象庁の発表によれば、全国の平均気温は平年より2.34℃高く、1898年の統計開始以来、過去最高を記録した。これまでの記録(2020年の+1.43℃)を大きく上回る異例の数値だ。
「6月ってこんなに暑かったっけ?」という感覚は、もはや錯覚ではない。私たちは“異常気象”という言葉を使い続けてきたが、もしかするとそれは、すでに“新しい日常”なのかもしれない。
🔹「暑さ」が問いかけるもの
この暑さは、単なる気象現象ではない。都市化、エネルギー消費、そして地球温暖化――私たちの暮らしの積み重ねが、気温というかたちで跳ね返ってきている。
6月中旬以降、太平洋高気圧が勢力を強め、全国的に真夏のような暑さが続いた。この現象は、気象の話にとどまらず、社会のあり方や未来の暮らし方を問い直す契機でもある。
🔹「暑さ」とどう向き合うか
この夏の暑さは、単に「耐える」ものではなく、「備える」ものへと変わってきている。
企業は働き方の見直しを迫られ、学校では熱中症対策が日常化し、家庭ではエアコンの稼働時間が伸びる。エネルギー消費と健康リスクのバランスをどう取るか・・・それは、私たち一人ひとりの選択に委ねられている。
🔹おわりに:気温の記録は、未来へのメッセージ
「6月はやっぱり暑かった」。この言葉が、ただの感想で終わらないように。
記録的な暑さは、未来からのメッセージかもしれない。
私たちは今、気候と共に生きる知恵を問われている。
そしてその知恵は、日々の小さな選択――たとえば、冷房の温度設定や移動手段の選び方――から始まるのだ。
さて話は変わって、
人材育成においては、さまざまな葛藤や対立を経験することが多いものです。上司と部下の関係であっても、表面化しない衝突を感じる場面は少なくありません。こうした葛藤や対立、衝突といった「コンフリクト」は、人材育成に限らず、集団で仕事をする上で避けては通れない要素です。
しかし、コンフリクトをネガティブに捉える必要はありません。解消に向けた過程を通じて、部下が大きく成長したり、育成上の課題が自然と解決されたりすることも多くあります。
このコンフリクトを解決するためには、さまざまなアプローチが存在します。その鍵となるのが、「自己主張」と「他者の主張への理解」であると言われています。中でも望ましいのは、「協力」による解消です。
ただし、上司と部下の関係性では、どうしても部下の自己主張が抑えられ、上司に対する理解だけが先行しがちです。これでは一方的な押し付けとなり、健全な関係性の構築にはつながりません。
自己主張と他者理解の強弱によって、対立への対応は次の5つに分類されます。
– 回避:対立があることを表に出さず、問題から距離を取る
– 競争:自己の利得を優先し、相手を抑えつけようとする
– 和解:自己の利得を放棄し、相手の主張に譲る
– 妥協:双方が譲り合えるポイントを探って折り合いをつける
– 協力:双方が協力して、問題の根本解決を目指す
このうち、「協力」以外の方法では、上司・部下いずれか、もしくは双方に不満が残ることが少なくありません。そのため、人材育成においては、上司からの働きかけはもちろん、育成される側の積極的な姿勢や協力的な態度が不可欠です。
では、「協力」に至るには何が必要か。それは、日頃から円滑なコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことに尽きます。自分の考えや計画を相手に的確に伝え、同時に相手の立場や背景、考え方を理解しようとする姿勢が求められます。
とはいえ、状況によっては「協力」だけでは対処しきれない場面もあるでしょう。そんなときは、他の4つの解消法もうまく使い分けながら、最終的に「協力」を目指していくことが現実的であり、実効性のある対応といえます。