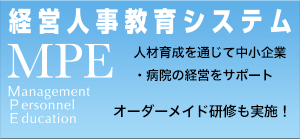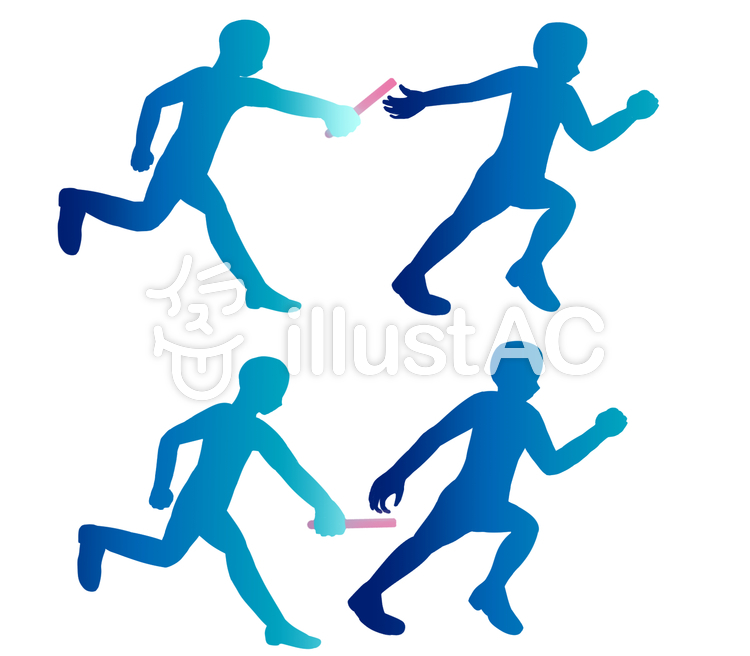
みなさんこんにちは。下ちゃんです。令和7年9月22日月曜日です。
#人材確保等支援助成金 #Goodモチベーション診断 #人事制度設計 #組織診断
#リカレント教育 #賃金制度設計 #採用・定着・戦力化支援プログラム
https://www.mpejinji-club.jp/568
https://www.mpejinji-club.jp/jinji https://www.mpejinji-club.jp/
全員が、今できる力を出し切ったのだと思います。
男子400メートルリレー決勝では、日本(小池・柳田・桐生・鵜沢)は38秒35で6位となり、3大会ぶりのメダル獲得はなりませんでした。急な大雨の影響もあったのではないでしょうか。
9日間にわたる世界陸上は、数々の感動を届けてくれました。日本開催という特別な舞台だったことも、その熱気を後押ししたように感じます。
次回、2027年大会は中国・北京での開催。そのとき、日本の選手たちがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今から楽しみです。
さて話は変わって、
成果を出せなかったとき、どう上司に報告するか
誰しも「仕事ができる人」になりたい。成果を出したいと願っている。しかし、現実にはさまざまな事情で、期待通りの成果を出せないこともある。
そんなとき、上司にどう報告するか。どんな「反省の弁」を口にするかによって、その人の「人となり」が見えてくるという。では、よくある反省の言葉を見てみよう。
①「努力不足でした」
上司に「なぜ目標を達成できなかったのか?」と問われ、「努力不足でした」とだけ答える人がいる。もちろん、この言葉自体が悪いわけではない。自分では十分な努力をしたつもりでも、結果が伴わなかったということは誰にでもある。
しかし、「努力不足でした」だけで終わってしまうと、次につながらない。上司もその一言だけで納得することは少ないだろう。まずは、成果を出せなかった原因を自分自身で主体的に掘り下げる姿勢が求められる。
②「不徳の致すところです」
「どうしてこのような結果になったのか?」という問いに対して、「不徳の致すところです」と答える人もいる。これは、40代・50代の課長や部長が経営陣に対して使うことが多い表現だ。
しかし、あまりに形式的で感情がこもっていないように聞こえるため、繰り返すと信頼を損なう可能性がある。言葉の重みが伝わらないと、真摯な反省として受け取られにくい。
③「すべて私の責任です」
これもまた、マネジャー層がよく使う言葉だ。重い責任を感じているからこそ、「すべて私の責任です」と言うのだろう。その気持ちは理解できる。
ただし、このように言われたとき、上司が「そこまで君が責任を感じる必要はない。私にも責任がある」と返すことは、現実には少ない。責任を一手に引き受ける姿勢は潔く見えるが、具体的な改善策や学びが伴わなければ、単なる自己犠牲に終わってしまう。
成果が出なかったときこそ、自分の言葉で状況を整理し、次につながる対話をすることが大切だ。反省の言葉は、単なる謝罪ではなく、信頼を築くための第一歩。言葉の選び方ひとつで、あなたの「人となり」が伝わるのだ。
明るく挨し、心に芯を、運は信じて、縁を結び、目指すは遥か、大きな夢